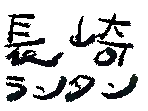
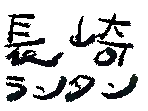
(この作品は「広島県医師協だより」2002年、6月から8月まで連載したものに加筆した。)
レースのカーテンを通して、明るい陽射しが壁に透かし模様を作っている。
珈琲の香りとビルエバンスのピアノが溶け合って、休日の朝を演出していた。
ボクがいつものようにEメールをチェックして返事を書いている時、
ダイニングで新聞のチラシを見ていた奥様の声が聞こえてきた。
「ねえ、ねえ。長崎へ行かない?」
「長崎って、何しに?」
「先月、上海格安ツアーに行ったけど。今度も、やはり中華なんよ」
「美味しいチャンポン大会なら良いけど、皿うどん食べ放題はダメなんよ。
昔から、あれを見ると食欲がどどーっと落ちるんよ」
「そんなんじゃなくて、ランタン祭り」
「あー、ハイハイ。赤いランタン波間に揺れて、カモメが啼いてる夕暮れ波止場。
それでは歌ってもらいましょう。波止場だよおとっつあん!みたいな、ランタンんね」
「なんかヘンだけど、そのランタン」
「OK、行きましょう。早速、申し込もうじゃないの」
こうして往復バス中10時間、長崎滞在4時間の日帰りバスツアーとなった。
こうなりゃ、缶ビール持って乗り込むしかないわけで。
(注)長崎ランタン祭りは、長崎の冬を彩る中国絵巻と言われる。2002年は2月12日(火)から2月26日(火)までの15日間、長崎市内は中華一色となる。長崎市街地では、湊公園、唐人屋敷、浜んまち、築町、鍛冶市、円山公園、興福寺などで各種イベントが繰り広げられる。その内容は、中国獅子舞、中国雑伎、龍踊り、民族音楽演奏、皇帝パレードなどである。歴史的には中国の旧正月を「春節祭 (しゅんせつさい)」として祝うもので、中国や台湾、香港でも「灯籠節」として盛大に行われている。 長崎でも在留する華僑の人々により、新地中華街を中心に「春節祭」が行われていた。平成6年から長崎市が参画して規模を拡大し、「長崎ランタン フェスティバル」となった。長崎の冬を彩る一大風物詩として、多くの市民や 観光客が楽しむものだ。新地中華街はもとより、長崎市内は、12,000個にも 及ぶランタンが長崎の街を光の華で色鮮やかに染め上げ、長崎の中の中国という 雰囲気を存分に楽しめる。メイン会場となる新地中華街に隣接する湊公園では、景徳鎮などの陶磁器を組み合わせて作った「龍と鳳凰」のほかに、本場中国から買い付けた大型オブジェを始め、今回は、2002年の干支である馬をモチーフにした「飛馬」など新しいオブジェも設置され、幻想的な中国独特の灯で街はまさに中国一色へと変貌する。期間中は、安全祈願やカウントダウンによる点灯式「春節礼祭」で開幕し、「龍踊(じゃおどり)」や「中国獅子舞」「中国雑技」と中国色あふれる多彩なイベントが毎日開催される。2月16日(土)と2月23日(土)には「皇帝パレード」、2月17日(日)と2月24日(日)には「媽祖行列(まそぎょうれつ)」が行われ祭りムードが更に盛り上がるそうだ。参考http://nagasaki-lantern.com
MIHI夫婦のスケジュールは、2月23日(土)10:20集合で解散が0:20 だった。
長崎滞在3−4時間の、無謀かつ過酷なバス乗り放題ツアーなのだ。だがこれはまだいい方で。
気の毒なほど乗りまくりの方は朝7:30集合で、解散が夜中の2:30。
この過酷さは、真夏の炎天下にトウバンジャンで味付けをして青唐辛子を振りかけたアツアツおでん大会に匹敵する。
もう少しで山口を脱出する港町に来た頃には、カンビールをズズっとすすってゴミ袋へポイ。
町中を走るバスの窓から、「スナック虹」の看板の「虹」の文字を見て思い出すのは加藤先輩。
ヤツが小倉の兵隊酒場「虹」の常連だったのは、医局員で知らないモノは居なかったほど。
この看板を見たとき、フツフツとサスペンスがボクのCPUに湧いてきたのだ。
このバスツアー体験記は、サスペンス仕立てになりそうだ。
何故か?と言うと、¥100ショップで見つけたサスペンス。
わが家の経済状態を省みず、一挙に5冊を買いこむ太っ腹を見せてしまったことがその発端だ。
勢いづいて?更に5冊購入となったお銚子乗りでもある私の凄さは、他の追従を許さない。
この赤ん坊以来のお銚子乗りだけは、夜中に声を大にして自慢出来る。
300ページを2−3時間でぶっ飛ばし読みの才能を発揮しつつ、
1/3読み終える前に我が明晰なCPUはトリックも殺し方も解析してしまうのに気がついた。
嗚呼、何という快感!何という単純明晰な頭脳!
で、サスペンスにはまってしまったのだ。
挙げ句の果てに自分のホームページに医学サスペンスを1編書き上げて、
溢れる才能を披露したほどだ。
明らかに嫌がる後輩に向かって、
「ボクのサスペンス処女作を読みたまえ。プロローグだけでも凄すぎて、途中でやめられないかもネ。
体をこわさない程度にゆっくり味わって読んでね。けして、14分で読み飛ばそうなんて思わないように。
ああ言うのを、スルメやスコンブのような味わいのある文章って言うんだろうね。
まあ、匂いはきつくないけどネ」と言いつつ、
「明日までに、徹夜をしても良いから読んで感想を聞かせてね。論文を書くのは、後回しで良いから」
を忘れない私はとっても後輩思いなのだ。
推理小説新人賞をもらったら土手医者と人気作家は両立できんナーなどと、人一倍謙虚な私は思ったりして。
この謙虚さが、痛々しく思うやら情けなく思うやら。

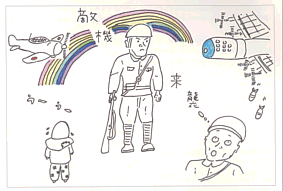
港町をバスが走り抜けるのにおよそ15分。
僅かな時間にも、こんな白日夢を見るのは才能の問題か?
頭を傾けるだけで,耳からこぼれ落ちる才能。
先日、鳥の糞が私の頭を直撃したときなどは左の鼻からこぼれて落ちた才能。
そう、私は鼻中隔湾曲症に通年花粉症を患っているので何とかこの程度で居られるのだ。
両方の鼻の穴が通っていたら?と思うと、不安で9時間以上は眠れない。
私の発酵した脳味噌はほんの一本のビールで、「虹」という言葉をインプットされて奇怪なストーリーを生む。
---
ボクが初めて学会発表をしたのは、第1856回循環器学会の総会。山口医科大学教授が退官するのだ。
大学を去る前に、花道とも言うべく学会を担当するのが僕たちの世界での習わしであった。
四国の我が詫間大学医学部第12内科の医局員は、ほとんどが山口へ向かった。
ボクにとっては、デビュー戦だ。たった7分の発表時間のために、原稿を何回読んだか分からない。
だから、目をつぶっても発表が出来た。ボクの発表は初日であり、それが終わったら観光のはずだった。
さすがに生まれて初めての学会発表を前にして、緊張感は最高潮に達していた。
4年ほど先輩の加藤慎司と同じ部屋だったのが、ボクの運命を変えた。
「幹、飲みに行くぞ!景気づけや」
「あ、ボクは明日が発表ですので。今夜は…ちょっと」
「アホ言うな。考えたって無駄やぞ」
「そう言うものですか?」
「当たり前やないか。ググーッと楽しく飲んで、脳味噌から水虫の足まで全身すっきりさせて発表や!」
「はあ…」
「出発進行で、突撃イ!」
滅多に使わない「突撃イ!」に、凄く力が入っていたのが気になった。
加藤先輩とボクは、コーフンしながらタクシーに乗り込んだ。ホテルからおよそ15分であった。
ボクは初めての山口で、何処をどう走ったか全く覚えていない。
「ハイ、着きました」
温泉街の大通りから少し入った店の前で、車のドアが開いた。
地味なトタンの看板に、「兵隊酒場 虹」と毛筆風に書かれていた。
「先輩、ここですか?」
「ここや、山口じゃ今度で2回目なんや。一度来たら、忘れようと思っても思い出せない。
あ、違うわ。忘れられないじゃ、ワハ。さあ、突入するぞオ」
この時は、加藤先輩はかなりの余裕を見せていた。
木製の重いドアを開けると、そこには兵士の格好をした男が居た。
「いらっしゃいませ、ここで着替えていただきますが。どのようにいたしましょうか?」
「こいつは3等兵で、ワシは2等兵や。ハイ、このカードで良いんでしょ?」
先輩は、日の丸が入った橙色のカードを差し出した。
「あ、2段目でいらっしゃいますか。では、こちらへ」
「先生、2段って?」
「これはナ、通う度にカードのメモリに記録してもらうんじゃ。
一杯になると段が上がって、虹の七色の順番に色が変わるわけ。
虹の最後の色は紫やろ。その次が、金色。これで大将になるんじゃ。
関西にはチェーン店が県に一つはあるから、何処でも使えるわけよ」
2畳ほどの部屋へ通される前に、一抱えもある風呂敷を持たされた。
「何ですか、これ」
「制服や。いや、軍服や。着替えたら、自分の服をたたんで包め」
「なんで飲みに来て、こんな格好しないといけんのですか?」
「ごじゃごじゃ言わずに着替えろ!」
先輩の口調がだんだん命令口調になってきたのに気がついた。
加藤上等兵の威厳は、胸の金ぴかのボタンと同じくらい輝いていた。
さらに奥へ進むと、鉄製のドアがあった。
その目の高さの辺りには、小窓があってその下の小さなボタンを押した。
カチッと言う音と共に小窓が開くと、ぎらぎらした男の目がボク達を見つめた。
ボクはチョットひるんで、目を伏せた。
低いこもったような男の声が、小窓を通して聞こえてきた。
「お二人ですか?」
「あ、ハイ」
「どうぞお入り下さい」
「ガチャ」と金属音がしてドアが開いた時、「突撃!」という声が耳にぶつかった。
「な、何ですかここは?」
「まあ、簡単に言うたら…兵隊ごっこをしながら飲むところかな。さしあたり、お前は三等兵や」
「さ、三等兵ですか!」
「指揮官殿、手榴弾と玉砕を一杯ずつお願いします」
背筋をピンと伸ばし、右手は敬礼状態の先輩。
「センセ、凄いものを注文したんですね」
「ああ。覚悟して、しかもありがたーくいただくように」
「か、覚悟ですか。しかもありがたく…ですか」
手榴弾は焼酎をラムネで割ったものであり、ボクには飲みやすかった。しかし玉砕は臭いがきつかったし、一口啜ると口の中が焼けた。そう、やけ火箸を7,8本一気にくわえた感じと言って良いかも。舌の感覚が一斉に消え、喉はヒリついてしまいただただ熱い。ええいナムサンとばかりに飲み込むと、食道・胃・十二指腸・小腸までその位置が確認できるくらい焼ける。
「センセ、これ何ですか?ホントに口から飲んで良いんですか?」
「アホ。こんなもん肛門から中へ注いだら、腸が南京玉スダレみたいになるで」
ボクは丁重に辞退した。あとで聞くと、玉砕はウオッカ+赤唐辛子+ニンニクエキスをジューサーで撹拌したものらしい。その上があることも聞いた。なんでもそれは、爆弾三勇士って言うらしい。作り方は簡単で、テキーラ+青唐辛子+豆板醤をジューサーで撹拌するだけ。どちらも、この世のものとは思えない。加藤先輩は2杯ずつ一気にいただいてしまった。この合計4杯は、先輩の顔の色を赤から土気色に変えた。
「幹。お前は、三等兵だろ。ブヘー。分かるか、その意味が」
「意味って言ったって…」
「何か食料を調達してくるのじゃ、ウーップ、ギモヂ悪りい。とにかく貴様は、あそこの従軍看護婦に言うて来るのだ。上官の命令は、良いかア。恐れ多くも、陛下のお言葉だぞヨ」
女給風な女性を見ながら言った時、けたたましくサイレンが鳴った。ウー、ウー、ウー
「敵機来襲、敵機来襲!」ドドドドド……と、スピーカーの音はボクの鼓膜を震わせた。
「キグチ・コーヘイは死んでもラッパを離しませんでしたア」そう言って、テーブルの上にあった泡盛をラッパ飲みする加藤先輩だった。
「先輩。無茶をしては」
「やかましい!上等兵の言うことが、耳に入らないのか」
「あ、先輩!さっきは2等兵って」
「じゃかあしいワイ。ゲフー、うーギモチわりー。足を開けー、歯を食いしばれー」
そう言ってボクのほっぺたを、ありったけの力でひっぱたいた。いや、そうしようと思った。
振り下ろした腕の勢いでふらついてしまい、空を切った腕は一回転してボクに抱きついた。
「2等兵じゃったかいな、ボヘー。行くド、2等兵の心意気を見ておるんじゃ!」
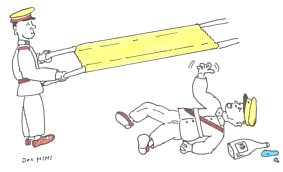
ゴボッ、ゴボッと音をさせて一升瓶は空になった。
その瞬間後ろへ倒れ込み、泡盛を鯨の潮吹きのように吹き上げた。
そのまま裏返った亀のように仰向けになって、床の上でのけ反った。
「戦傷者をタンカに乗せて撤収ウ」いつの間にか、指揮官と呼ばれた男が先輩の傍にタンカを持って立っていた。
「介抱室へ!」そう言いながら、二人の男は先輩を連れ去った。
「海イ、行かばア……」日章旗を振りながら、突然に飛行兵の格好をした男が歌い出した。
手榴弾が効いてきたのか、何が何やらワケが分からなくなった。
その時、将校の姿をしたボーイッシュな女性が近寄ってきた。
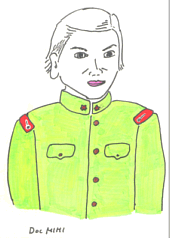
「加藤先生は、相変わらずですね」
「あ、どうも。貴方は?」
「加藤先生とは、仕事でご一緒したことがあるんです。
先日、学会で山口へ来られるってメールがあって。お別れを言おうと思って、ここへ来たんですけど。
今夜は、自爆しましたね」
「まあ、そう言う感じですね」
「3年前まで、一緒のところで働いていたんですけど。ここのお店には来られなくなりそうだし」
「どちらに行かれるんですか?」
「はい。昔、住んでいた長崎へ」
「長崎ですか。一度、学会で行ったことがありますよ」
「あ、そうなんですか」
「ええ。とっても大きな茶碗蒸しを食べさせてくれる老舗も、その時行きました」
「あ、あそこは有名ですね。私も何回か」
「お、幹!生きておったか。撤収じゃ」
日向の鯖の目で、ふらつきながら加藤先輩が近寄ってきた。
「先輩、大丈夫ですか?」
「今日は、撃沈や。ありゃ、あんたは…えーと」
「ハイ、坂根知代です。お久しぶりです」
「おお、そうそう。坂根くん。元気やったか!ウップー、ボヘー」
「実は私、来月の末に長崎へ帰ります。もうお会いすることはないでしょうね。」
「そうか、長崎か。勝利を祈る!」
そう言って、先輩は膝から崩れた。
「じゃあ、お勘定をして帰りますか」
「それが良いわ」
玉砕2杯、爆弾三勇士2杯、手榴弾3杯で9000円は良心的なのだろうか?と思いつつ、
我々は白旗をかかげながらホテルへ退却した。
メチルアルコールを飲まされなかっただけマシかも知れないと思った。
その後、加藤先輩はオヤジさんのあとを継いで故郷の佐賀で開業した。
開業パーティに招待されて出会った時には、5年の年月は全てお腹の脂肪となって貯まっていた。
この年にボクは見合結婚をして家庭を持ったから、先輩との悪夢は終わらせることが出来た。
---
ここまで来て酔いが醒めた頃には、既にバスは九州だった。
バスの中は、夜のランタン祭りに備えて熟睡の響き。
大口を開けて爆睡中のオヤジを見ていると、次のストーリーが浮かんで来るではないか。
自分の才能が恐いと言うより、そう思う単純さの方がもっと恐い。
バスツアーの中には、大抵一人や二人はキャラクターの濃い人がいるものだ。
今回のツアーはキャラ沢山というか、濃いめの人が多かった。
その中でもこの夫婦は、異色だったと言える。
どくとるMIHI風に言わせて貰うと、商店経営夫婦という設定になる。
---
例えば老舗の菓子屋を営む飯田清である。
彼は、長崎などはどうでも良かった。
妻の早樹に勧められて、嫌々付き合っただけだ。
商店街の店主で作った「極楽クラブ」のゴルフコンペを断っての参加だったから。
彼の店は和菓子を売って60年の老舗である。
そんな彼は子供の頃からおやつに和菓子しか食べさせられたことがないので、和菓子にはヘキエキしていた。
大人になってオヤジの言うことを聞く必要が無くなってからは、大ぴらにパンばかり食べるようになった。
あんパン、クリームパンも良いが、メロンパンが気に入っていた。
それより何より、細長いクリームサンドが気に入っていた。
特に、フランスパン生地で、噛みごたえのあるやつが好物だった。
年の割には歯が丈夫で、たまに歯医者に行くと「良い歯をしていらっしゃいますねー、歯茎なんか高校生並みですね」って言われるのが自慢だった。
彼にはこの日に長崎に行きたくない理由がもう一つあった。
コンペの打ち上げ中に抜け出して、スナック「パッポンQ」のママ藍田匡子と落ち合うつもりだったのだ。
「今度の土曜日、あなた何かご予定は」
「あ、うん。ダメだ。予定が入っている。ゴルフコンペだ」
「えー。たまには奥さん孝行をしてもバチがあたらないわよ。1日だけ付き合ってね」
<清に言わせりゃ>
ホントに、冗談じゃあないよ!
そりゃあ、最近はケーキや和菓子よりハイカラなカタカナのお菓子が売れているけれどネ。
明治から続いた老舗には、カタカナのお菓子なんてえモンは作れっこないさ。
こんな古い店はたたき壊して貸しビルにでもすりゃあ、家賃の上がりで暮らせるってえもんだ。
あとは、趣味の釣りでもして。年に一回温泉でも行けば、あたしゃ満足だね。
時々、スナックのママと美味しいものでも食べに行けりゃ言うことはないな。
まあ今回のおつき合いで、ばれた浮気はチャラにしてもらうとして。
しかしなんだね、女房は年々小うるさくなって来るんだね。
昔は良い女だったけど、控え目で楚々としていてね。
町内じゃあ「小町」って呼ばれるくらい、浴衣姿が粋だったんだ。
たまにバアさんの代わりに店番をしていると、若い奴らがちょっかいを出すきっかけが欲しくて店の前を行ったり来たり。
あいつが何気なく外に目をやった時に、通りがかった若い衆と目でも合ったらえらい騒ぎでね。
「小町」はあたしにほの字だね。あたしを見つめるうっとりしたあの目つきは普通じゃないね!なんてネ。
かく言うあたしも、そんな若い衆の一人でもあったんだけどね。
今じゃ、ひどいモンだよ。言ってみりゃ、詐欺か拷問だねあれは。
浴衣で両国を歩いていたら相撲取りと間違われるもんなー。
<清の女房に言わせりゃ>
ろくに仕事もしないのに、偉そうに腹だけ立派になっちゃって。
腹が出た分、髪の毛が引っ込んじゃってるから。もう、たまんないね。
その上菓子の食べ過ぎで、虫歯だらけ。
そこへ持ってきて、金歯を入れたものだからひどいモンさ。
ヤダ、ヤダ。あれじゃあまるで、禿げた獅子舞だね。
おてんとさまが当たると、顔全体がピカピカ光り輝いていて。
名古屋城の金の鯱じゃないっつーの。
こんな粋な女房がいるって言うのに、浮気なんかして。
今度という今度は、許さないよ。ホントに。
---
私は内痔核が出るほどの血のにじむような修行によって、1度も目を合わせなくても表情から嗅ぎ取る技術が体に仕込んである。
それを駆使すると、お互いの言い分はそう言う風であった。
単なる想像や勝手な解釈ではないことをご注意申し上げておく。
ここまで分析出来る自分の感受性の凄さは、犬の嗅覚かトリュフを探しあてる豚なみだな!と、ほくそ笑んだりして。
そんな私であるのに、なぜ初診の患者さんを一目見ただけで診断がつかないのか謎であった。
思い起こせば、バスツアーの謎はここ辺りから始まっていたのかも知れない。
まさか、あれほどの数の謎がこのバスツアーに潜んでいるとは。
バスは古賀インターにさしかかったところだ。ここでも謎が待ち受けていたのだ。
それにしてもよく食べるオバチャン連れではある。
あの体重を維持するための努力は並々ならぬ底力を感じるし、3重顎のふてぶてしさと強靱さからも確認出来る。
ここで、TV出たがり内田康夫氏が描く「名探偵の浅見光彦」ならツアー仲間の職業を一目見ただけで当ててしまうのだろう。
例えば、1組の若い女はナースであることはすぐに分かってしまう。トイレ休憩の乗り降りにかいま見る雰囲気。
それはすれ違う客に対する、患者に対するような物腰。患者さんを思って短く切った爪に、マニキュアの塗り残しを見逃さない。
しかも、左の薬指の爪が物語っている。爪に描かれた菊の花が、犬のコーモンに似ているのを見て嬉しくなった。
まあ早い話が、休みの日にしか出来ないのでネイルアートに熟練していないと言うわけだ。
少し離れて座っている若い男は、ナースの片割れの恋人のはずだ。
お互いに目が合うと男はニッコリで女は嫌な表情を作るから、最近あまりうまく行っていないことさえも分かってしまう。
景色を窓から眺めるのに、いつも両手の指で四角く枠を作っている。その上、「カシャ」なんて呟く。
だからフリーカメラマンの恋人と言う設定だ。そして、元教師らしい夫婦。
奥さんに「ガイドブックの37ページ。下から5行目。予習してきただろ?帰ったら、良く復習しておくように」という会話。
やや威圧的な言い方から、中学校の教師であったはずだ。
古賀インターでお店に途中下車すると、売り子のオバチャンが「お茶をどうぞ!」。
お盆に乗せた小さめの紙コップは、何やら怪しい匂いを漂わせている。
私はトリュフ探しの豚をペットにした友人が居るくらいだから、匂いのルーツが椎茸であることは飲む前からお見通しである。
乾燥したカビのような匂いは、かつて、お中元で干し椎茸を貰った時以来だ。
花粉症の私でもちょっと耳を澄ませば「この椎茸茶まずいわ!」と言うおばちゃんの声を聞き逃さないのもある。
私の聴力は、私の悪口と食べ物の話には過敏だ。聴診器などを使わなくても、5cm程度の壁なら糸電話より良く聞こえる。
ビールをいただいた結果、トイレ休憩が済むと眠りを誘う。
いびきをかく前に、カステラ業者「古里屋」からの試供品を配り始める。
今回は配りものが多いツアーはないと言いつつ、パンフレットやら地図やらを配りまくる添乗員。
こんな時、内田康夫氏のサスペンスを2冊読んだ影響はすぐに現れる。
早い話が、すぐに他人の影響を受けやすいだけかもしれないが。
私は何と言われようと、ここで「自分の感性の鋭さと無防備さ」を主張したい。
内田氏の作品の特徴は、主人公と一緒に出たがりなのだ。
だから、今回の文章も現実と創造の人物が入り交じってしまうのは仕方がないところだ。
けして言い訳とか、CPUが暴走しまくりや、脳みその99%がトロトロになっているのではない事を申し添えておきたい。
トイレ休憩が終わり、添乗員さんが客の数を数えて「じゃあ、出発します」と言ったが。
サスペンス好きの私なら、ここで1つの簡単なトリックを使う。
ツアーが始まったばかりの頃は、添乗員は客の顔を覚えていないはずだ。
その盲点をついて、犯人が入れ替わりアリバイ作りをする。
しかし、それでは「ド」がつくほどの素人の発想だ。すぐに話の中で刑事が気づく予定になっている。
例えばこうだ。
---

後で気がついたのだが、サングラスの女(飯田清が通うスナック「パッポンQ」のママの設定)が見えなくなっていた。
添乗員は乗客の数を確認する時、その事を知っていたようだったのはなぜだろう。
古賀インターを出て2時間した頃、「間もなく長崎です。では、今日の予定をお伝えします」
金融業者風な男が連れの女に起こされる
「あなた。ビールはもう良いの?」
「あ。そうか」紙コップに、残った缶ビールを注いだ。
ウグウグ…飲み干して43秒も経たないうちに苦しみだした。
「あなた!どうしたの?」
「グッ…」と言って前へ崩れ落ちたのを見た妻は、
「キャー、添乗員さん!しゅ、主人が」
「どうされました?御気分でも悪いんですか?」
前へ突っ伏した男の肩を、ぐいっと引き上げた。
その時、ナッツの匂いがした。
これが青酸カリを使った殺人であることは、サスペンスを愛読している赤ん坊でも言い当ててしまう。
その時の問題はただ1つ、赤ん坊がちゃんとした日本語を喋ることが出来ればの話だが。
フランスやオランダや中国の赤ん坊だったら、いくら頭脳明晰な私のCPUも謎としか言いようがない。
「ハイ、確かにお客さん以外にはバスに乗っていませんでした。31人だったのを確認しています」と添乗員は言う。
「服の色や背格好だけではなく、顔も確認したんだろうね」という刑事に。
「そ、そこまでは…」と口をつぐんでしまった。
「ヘタなTVサスペンスなら、そう言うド素人みたいなトリックを使うんだ。
私のようなベテランデカ(刑事ドラマではカビが生えるくらい古い表現だが)には通用しないがネ。
ガハ、ガハハ」タバコの脂で黒茶色になった歯を見せて笑いながら<こいつ何か隠しているに違いないナ>と言いたげに添乗員を見据える。
---
そうこうしているうちに、バスは謎と坂道だらけの長崎市内に入って行くのだ。
何と言っても、長崎の町の特徴は、自転車屋を見つけにくいことだ。
長崎の人は自転車に乗るよりも、屋根の上を走るか篭に乗って移動しているのだろう。
歩いている人はいたが、篭をバスの窓から見ることは出来なかった。
朝早くか夜遅くに篭が出回るのかも知れないと分析したが、新たな謎であった。
もう一つの特徴はカステラ屋が多いことである。
フツーの茶色いヤツ以外に、抹茶色、チョコレート色など様々で。
真っ黒のヤツを見かけたような気がする。
タブン、スペインかイタリア辺りから逆輸入した「イカスミカステラ」ではないか。
粗目の砂糖が付いた部分が好きなカステラ通の私であるから間違いない。
イカスミカステラに関しては、私の自慢(3万冊のモノで、3冊以外は倉庫に30年前からしまってある。
ただ、29年11ヶ月前に台風で何処かへ飛んで行ってしまったと近所の犬の噂で聞いた。
あの百科事典には掲載されていなかった。
しかし、真っ黒なカステラはその時以外見ることがなかったので、
もしかすると黒猫が昼寝していたのを見誤った可能性は否定出来ない。
これもついでに謎にしておこう。
オランダ坂を筆頭に、坂だらけの町長崎。濡れた石畳を滑りつつ登ると、グラバー邸がある。
不思議と長崎では、坂道は登る人が多い。
きつい下りは足早になってお互いに衝突する危険を察知しているはずだ。
だから、取りあえず店に入ってカステラのサンプルを食べることになる。
そういう理由で、どうしても登りの人数と下りの人数が違う。
もしかすると、時空の壁に穴が空いていて、そこから観光客がこぼれ落ちているのだろう。
それも謎だ。坂道をちょっと歩いただけでも謎だらけの長崎は次にはどんな謎を生むのだろうか?

坂道を上り詰めると、嗚呼そこはグラバー邸だった。
別に「長崎は今日も雨だった」を歌いながら登ったので、そういう表現になってしまったのではない。
だが、クールファイブは好きだ。入り口前に、管理事務所があり団体客でなければ¥600を払うことになる。
ここで後ろ向きに歩きながら、「あ、どうも。良かったねー」などと言いながら侵入しようとしてもばれるから諦めて払いましょう。
正規の入場により入り口を抜けると、足下がゴム製の動く登り坂が待ち受けている。
右下にグラバーさんちの裏が目に入っても見ないフリをして登ってゆく。

酔っぱらっていたり手すりにつかまっていないと、前につんのめりそうになる。
まあ、輪ゴムの二丁拳銃が出来るほど運動神経抜群の私が2度ほどつんのめったくらいだから。
一般人の方は、恐らく1回のつんのめりはあると予想されるが。
自動ゴム坂を降り立つと、右手チョイ下のカーネルサンダース似のプッチーニ像は後回しにして真っ直ぐ。

右手にウオーカーさんのお宅を見てちょっと歩くと、目の前に旧三菱第2ドックハウスが立っている。
船の模型に興味のある人には、3時間24分ほどの時間つぶしが出来る。
2階に上がると、テラスから池が見えたり港が見えたり。
何とかと煙は高い所に上がるらしいから、私達以外のここの客は全員何とかに近いモンに違いない。

オルト、リンガーのお宅をはしごしつつ眼前にグラバーさんの家が見えてくる。
南青山カフェテラス風のお宅を巡りながら、「そういえば、3日前に読んだ¥100サスペンスでは、ここで殺人事件が起こったな」と思い出す。
仮にグラバー邸でナースの死体が発見されるとする。
私のトリックは非日常的で、一筋縄ではいかない。青酸カリを針に塗った蜂を使う。
蜂は催眠術にかけられており、若いナースを見ると耳たぶに向かって突進して刺してしまうように仕組まれているわけで。
「長崎踏み絵殺人事件」矢島誠著(¥100)のグラバー邸での密室殺人トリックよりも難解で、しかも誰も思いつかない唐突なトリックだ。
かの江戸川乱歩さえ、この猟奇じみて呆れたトリックは思いつかないであろう。
たったこれだけでも、江戸川乱歩賞を既に手中に収めてしまったと言える。
この時に使うペンネームは、既に考えてある。
「一の坂蛍」なのだが、いかにも西の京の風情と旅情を感じさせるネーミングだと我ながら感心している。
かの有名なドラマ「北の国」を思い出させる土臭さは、極限の庶民的な風格さえ感じられる。
ここで、幾つかの謎を他人に指摘される前に掲げておこう。
すなわち蜂に催眠術をどうやってかけるか、針に青酸カリを塗られた蜂は生きていられるのか。
そして、病院に紛れ込んだらどのナースを刺して良いかパニックになってしまわないのか。
1つのトリックだけでもこれだけ謎だらけのところが、恐いくらい呆れてしまう。
自分の才能に驚嘆・驚愕してしまい、もう途方に暮れて声も出ない。
研ぎ澄まされすぎた我がCPUを冷却し痺れさせるために、思わずここでカンビールを開けることになる。
1日2回アルコールを口にしないと、ちょっとだけ暴れるからではないことを確認しておきたい。
酒だ酒だ!酒持って来んかイ。ヒック・・・あ!
さらなる謎は、グラバー邸にあるベッドは何故小さいのか。
グラバーさんは、実は小学生だったのではないか。
そうでなければ腹話術の人形で、誰かが操っていたのではないか。
もしそうなら、壁に掲げてある彼の写真を見る限り精巧な作りの人形だ。またしても、1つ謎が増えてしまった。
<ああああー、長崎イは今日も謎オだああったーア>
坂道を半分ほど降りた右手に、大浦天主堂がある。
時間と小銭がなかったので、夫婦で「南無」と手を合わせただけで失礼した。
市営松が枝駐車場近く、グラバー邸を降りきった所でバスを下車。路面電車の線路を横切り、湊公園へ向かう。
公園近くになると、ポリスマンが交通整理をしている。
湊公園を取り巻くように、ボランティアの若者がおそろいのジャンバーで各所に立っている。
彼らの指導に添って、足下にソフトクリームを垂らしながら行くと、土地勘の鋭い私たちは自然に湊公園に着いてしまった。
交通規制をした道路。幾重にも歩道に並んだ人々は、ドラの音がする方向を覗いている。
ドラの音は聞こえるが、行列はなかなか来ない。
「音がすれども見えないなんて、ほんに貴方は屁のような」なんて言う三味線漫談を思い出すのは、
学問的な(確か私の矯味があるのは落語民俗学だったような)興味から出発して極めた寄席通の証拠である。
あたしがタダ(無料の意味でのタダではない)の医者でないことが、ここでばれてしまったが仕方がない。
実は、ある時は「詐欺師」、またある時は「内科医師」、
しかしてその実態は「生まれてこの方、一度も真実を口から発したことがない正直者」であるのだ。
まあ、強いて言えばサスペンスにはまりかけて、謎の溝に落ちて出られなくなった医者であろうか。
この風景を見ただけで、殺人トリックを思いつくほどにはまっているのだ。
例えば、皇帝パレード中にオバチャンが苦しみ出す。その周りには、沢山の人が居たが殺人の実行犯には気づかない。
犯人は、雀なのだ。鷹や鷲では、誰でも肩にとまれば分かってしまう。
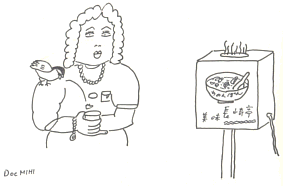
まあハゲ鷹が肩にとまれば失神することはあっても死ぬようなことはないから、雀が丁度良いだろう。インコでは派手すぎる。
肩にとまるに都合の良い大きさの雀がオブラートにくるんだ青酸カリをくわえて来て、オバチャンのジュースのコップに落とすのだ。
屁のような行列の方に、みんなの視線が集中している。
だから、雀が何をくわえていようが、オバチャンの肩にとまってくわえていたモノをコップに落としても気づかないはずだ。
ただ、雀にくわえた青酸カリを飲み込んではいけないことを、どうやって教えるかが謎だ。
謎を生む皇帝パレード。皇帝に扮した、商工会議所のお偉いさん。
でも、一番人気は誰が見ても貴妃の方で、シャッター音の数は1:9890(もちろん1が皇帝)。
新地中華街を通り抜けてきたパレードは、7―8mの道路を歓声を受けながら渡りきって、すぐに湊公園に侵入したらオシマイ。
中華街をパレードと共にやってきた群衆と、逆行しようとする群衆で1平方メートルに10人は存在していたカンジ。
「足を踏まないでください」って言いながら、僕のスニーカーを何度も踏んだお兄さん。
人混みの中で足下が確認できなかったが、人の足を踏んでいるのに踏まれているように感じるヤツの靴の構造が謎だ。
夕食時にはちょっと早い5:00だけど、どこの中華レストランも行列だらけ。
ずんずん進むとアーケードが切れて、小さな橋が見えると急に明るくなった。
20mばかり行くと、左手に食堂を発見。しかも、誰も並んでいない!
穴場を発見したのか、入り口に見えるが出口専用なのか。
はたまた、入り口は高々4−5mだが中へ入ると2−3Kmはある細長い店で、3000人は収容出来るのか。
入るのをためらって、5分ほど電信柱の影で観察していた。
がしかし、いつまで経っても客が1人も出てこないのは謎であった。
夕食の時にも謎が出てくるとは、やはり謎の長崎であった。

入り口と出口が違うのか、食事を終えた客は裏から棺桶に入って店を出るのか。
それとも忍者になって気づかれないように出てくるのだろう。
かの夏樹静子氏でさえも舌を巻くであろうと、この洞察力に自分自身驚いたものだ。
そう驚いてばかり居ては、ひもじさはどこにも行ってくれない。
私達は、死ぬ気でこの行列の出来ない店に入ることに決めた。
このまま空腹で死ぬよりはマシと思ったからだ。
我々夫婦はキリシタンにちなんで十字を切った。
その後で、手を合わせつつ念仏を唱えながら店の戸を開けた。
実はお払いもしようと思って、神主さんを捜したが見あたらなかったのだ。
これが失敗だったかも知れない。
外人さんが4人いて、笑いながら定食を器用に箸でつっついていた。
壁にはメニューが手書きで表示され、「名物長崎チャンポン」に目が止まった。
この時ほど、メガネを恨んだことはない。
これが「名物かも南蛮」に見えたら、あのようなことはなかったであろう。
「ビールとチャンポン1人前、お造り定食1人前」に、聞こえたのかどうなのかはっきりしない従業員は立ち去った。
この時、空を見上げて「あ、飛行機。いや、スーパーマン」と叫びながら戸を突き破って表へ出れば
学食以下のチャンポンを食べることはなかったはずだ。
10分も待つと、テーブルにお造り定食とビールと枝豆が届いた。
普通の酒屋にある、普通のビールであることに安心した。
枝豆もちゃんと湯がいてあったし、それには砂糖ではなく塩もふってあった。
奥様が半分食べ終わったのに、僕のチャンポンはまだ来ない。
後から注文したチャンポンは、すでに3個も来ているのに。
26個ある椅子と、19人の客は既に把握していたから間違いはない。
のれん越しに私の姿を見た店主が、「一目見てわかるグルメの客には、自信作が出来るまで出せない」と思うのは正解だな!と思った。
だが、2分後に無惨にその解釈はうち砕かれた。
テーブルの上に置かれたチャンポンは、極ごく・超ごくフツーのチャンポンだった。

あんなに失望したのは、某レストランで隣の人が飲みきったミルクセーキの中にゴキブリの足を発見した時以来だ。
隣人の飲み物の中にあった嬉しくなる(当事者以外にとってはの話だが)異物のことを教えたくて、
けしてお節介ではなく人一倍親切な私は後を追った。
駐車場で見失ったときの失望は言葉では表現しがたく、じたんだを36回も踏んでしまった。
どんぶりの中を見渡すと、ピンク色の長さ2cm薄い蒲鉾を発見してしまった。
その他の具を思い出すと腹が立って体のふるえさえ感じる。
我が大学の学生食堂のチャンポンに、65.3mは遅れを取っていた。
これが名物だったのか!チャンポンなどを一度も食べたことがないままに、
この店の主人は色んなものを想像しつつ制作しているのだ。
参考書は「初めて行く長崎のB級グルメの旅:¥100円以下で腹一杯」だろう。
Z級グルメ評論家の私にはお見通しである。
知らなかった、これが本場のチャンポンだったのか!
学食で口直ししなければと思った。
空いたビール瓶を取りに来たオバチャンが、学食のオバチャンそっくりだった。
そうか、ここで第2の人生を送っていたのか!と思うと、このバスツアーで初めて謎が解けた。
学生時代から30年は経っており、あの時オバチャンは60歳と言っていた。
すると、彼女は90歳か?しかし、どう見ても60歳だった。
1つ謎が解けて、新しい謎が1つ増えた。
名物長崎チャンポンは半分が限度であり、ビールを流し込むと表へ出た。
人通りが少し減ったものの、新宿なみであった。
入り口で私達と入れ替わりに入る客がいたので、数分後の不幸を思い合掌した。
新地中華街を引き返しながら、揚げたてのゴマまんじゅうや蒸したての桃まんじゅうを2個ずつ買った。
あんこで上顎を火傷させながら食道へ送り込むとひもじかった胃袋が安堵した。

日が落ちた湊公園では、中国の架空動物の張りぼてに灯りが入っていた。
グラバー邸の裾にある駐車場まで、ほろ酔い加減で歩いて5分だった。
良くあることだが、知らない土地では行きより帰りが短いと言うが。
謎だらけの長崎だから、帰りの道のりが行く道のりの1/3であっても不思議ではなかった。
帰りのバスの中は、すっかりイビキの嵐だった。
こうして、謎だらけのバスツアーは終わった。
いろんな出演者が出てきて、私が酔っている間に何処かへ消えてしまった。
バスを最後に降りたのが、MIHI夫婦であるから。
「長崎と山口の間で超常現象により蒸発したか透明人間になったに違いない」と、理路整然と結論した。
家の玄関を開けた時、12時をかなりまわっていた。
風呂上がりに焼酎ロックを半分飲んだとき眠気が襲ってきたと思うのだが、朝起きたらグラスは空になっていた。
いくら私でも、焼酎を全部のんだかそうでないかは分かっている。
夜中に「座敷わらし」が飲んでしまったか、
夜中に生じた時空間のひずみによりリビングの湿度が急激に下がって焼酎が急速に蒸発したのか。
これが最後の謎であった。
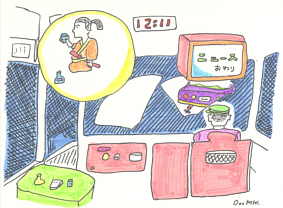
謎だらけの長崎ランタン祭りは、わが家で最後の謎を残して幕を閉じた。
夢の中に焼酎を飲む若い侍が出てきたのを思い出した。
髷を結い、腰には刀を差していた。
そう言えば、宮沢賢治の「座敷わらし」と同じ姿だ。
もしかすると、彼が残りの焼酎を飲んでしまったのか?また新たな謎が生まれた。
長崎とは、なんと謎の多いところだろうか!
