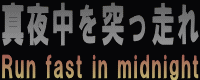
とりあえず、俺達のことをみんなに違和感なく知ってもらうために
その夜は零奈と話し合いをした。
「……じゃあ、あなたは私の親戚。私は社会勉強のために田舎から来たってことにしようよ」
「ちょっと無理がありそうだが、その方が真実味あるかもな。でもそれじゃ赤の他人てのは言い過ぎだよ」
「そうだな、じゃ私は親戚の知り合い、というのはどうかな? 」
「なるほど。それで俺達は知り合ったばかりてことで」
「そうすると、赤の他人にグッと近くなるね」
なんか赤の他人にこだわって馬鹿みたいだな。俺がそう言うと、零奈は笑った。え? 笑った? 俺の言うことに?
…………
「どうしたの?急に静かになって……」
あれ?これが零奈の言葉?いやコイツなら「どうしたんだ?急に黙り込んで、虫歯でも痛むのか? 」とか言うはずだよな。
「おまえ、喋り方変わってないか? 」
「えぇ?そうかな?別に変わってないと思うけど」
いや、こいつが気づいてないだけだ。以前よりすごく柔らかい口調になっている。この世界での生活で、こいつに変化が起きたのかもしれない。ものは試しだ……
「……布団がふっとんだ」
くーだらないギャグを飛ばしてみた。
「なによ急にぃ……ちょっとだけ面白いよそれ。ちょっとだけね」
親指と人差し指でちょっとだけと示し、クスクスと笑う零奈。間違いない、こいつは変わってきている。
いやはや、なんていうか……可愛い。いや今まで思わなかったわけではないがさらに増して、この口調。この笑顔。
零奈に欠けていた人間的な部分が、段々出てきたように思う。
こいつの笑顔は春の陽の様だ。黒い髪にスチュワーデスのようなセミショートカット。首の上にちょこんと乗った整った顔。ノーメイクでも朝の湖のように透き通った肌に、バービー人形のように長い手足。
いかん。俺はこいつに惚れかけてるのか?だめだ、こいつは暗殺者なんだ。血も涙もない冷徹な……
「リョウタ。これピアノ?」
零奈は急に俺の置きっぱなしのキーボードに手をかけた。
「あ?ああ、俺のバンド仲間がそこに置いてそのままにしてたんだ。俺はギターしか弾けないし、邪魔なんだよなぁ」
零奈はカバーを外し、椅子に座る。
「おまえ、弾けたの?」
「少しだけね」
それが弾けたのなんの。プロじゃないかってくらい上手かった。
指の一本一本がまるで鍛冶職人のように力強く鍵盤を打っている。
流れる音は一つ一つが正確で狂いがない。
川の水のようにとめどなく溢れるメロディーは、安物のキーボードとは思えないほど素晴らしかった。
「すげぇじゃん零奈!」
いや正直驚いた。こいつにこんな才能があったとは……
「組織ではね。なんでもできないといけなかった。乗馬やテーブルマナー、ダンスにバイク。でもその中で唯一楽しかったのが、これ。音楽って素敵だと思う」
キーボードに手をかけ見つめる零奈。
「俺もそう思うよ。いや俺のバンド仲間は途中でみんな止めちゃってよ。どうしようかと思ってたんだが、零奈! 俺とバンドしねぇか!?」
「私と……」
不意に零奈が下を向いて黙り込んだ。
ええ?嫌……なのか?それはちょっと、いやかなりショックだなー。そうだよな。俺のアマチュアギターじゃ釣り合わんし、俺とお前じゃ釣り合わんし。
俺の考えとは予想外に、零奈は微笑んでこう言った。
「リョータは素敵。よく分からないけど素敵ね」
なに?そんな事言われたら、よく分からないけど嬉しいじゃないか。
「リョータは私にはもったいない。私なんか消えちゃえばいいのに」
何を言う。日本中の男に聞いてみろ。俺とお前なら、間違いなく俺のほうが消されちゃうぞ。
「組織は嫌だ。私に人を殺させる。それで私自身を殺していっているのに。だから私は逃げたんだ、人を殺さなくても生きていける世界に。そして、そこにあなたがいた」
──俺は言葉を失った。そうだ、何回も自分に言い聞かせたじゃないか。無時零奈は暗殺者。
でも漫画や映画で見るような冷酷な奴らではなかった。こいつは人の死を背負いながら生きている。もしこいつが狂人で、人を殺すのが趣味だったらきっと、毎日楽しくてしょうがないだろうに。
そうじゃないんだ。こいつは人並みの感情を持っているが、それを深く押し込めている。
無時零奈は普通の少女だった。
俺は人を殺したことがないから、こいつの悲しさはわかりゃしない。
いつまでも解けないルービックキューブのように。
「夢中だったけど、楽しい事なんてなかった。撃たなきゃ死んじゃうんだよ?一瞬の判断が命取りで、それでどうしろって言うのよ!? 相手だって死ぬ気はないわ! でも私だって死ぬ気はない!」
どうしようもない。生きるためにはどうしようもないだろう。
問題はこいつをそんな状況へ追い込んだ組織の奴らだ。
これは個人の力ではどうしようもない事なのか?
──いいや、違うぞ。
「うわっ何!?」
俺は零奈を抱き上げた。そう、お姫様抱っこだ! うわあああああぁあ……
この世が沸騰しそうなくらい俺の頭は熱くなっている。
勢いで部屋を出て迷わず、飛び降りた。ここは2階? 知るか!
ドンッというにぶーい音がした。痺れる〜
「ちょっとリョータッ! 大丈夫なの!?」
「う……大丈夫じゃない。いいから車に乗れ。いいか、運転席だぞ?」
俺は零奈にキーを渡した。
零奈は状況が飲み込めていない。俺自体もそうだ。
「でも、16歳は乗っちゃ駄目なんでしょ? 」
「知るかよ。なぁ、知るかよなぁ。この真っ暗な夜に16歳の女の子が運転したって、誰が気づくかなぁ……?
いいんだ、こういうこともあるんだよ。悲しい夜には誰だって走りたくなるモンなんだ。零奈、車を飛ばせ!道なんか知らん。適当に飛ばせ! 」
「……わかった! 」
あの駐車場での空ぶかし。今日は前より勢いが違う。
零奈が発進させたとたん、そのとたん、夜の道路はサーキットに変わった。
流れる街の光や街の喧騒を背に、あっと言う間に郊外へ出た。
零奈、この世の中には悲しいことなんてどこにでもあるんだ。みんな一緒、お前は独りじゃないぞ。
──ただ今は車を飛ばせ!俺達にできる最高の夜の過ごし方を。
なんてスピードだ! 羽さえあればこの車だって飛べるぞ!
「ねぇ! これなんていう曲?」
「ジョン・レノンの『Whatever Gets You Thru The Night』──邦題は『真夜中を突っ走れ』だ」
「真夜中を……真夜中を突っ走れ……か!」
そうだ突っ走れ! この不条理でどうしようもない世の中で、少しだけ自由があるとするならば──
どうやって人生を過ごそうとも──
いいのさ それでいいんだ
間違って生きたって 正しく生きたって──
いいんだ それでいいんだ
ぶらぶら過ごすのに腕時計はいらない
そうさ いらないぜ
さぁ抱いてくれ そして聞いてくれ
君を傷つけたりはしない
僕を信じて──頼むから
僕の言葉を聞いてくれ──
『Whatever Gets You Thru The Night』 John Lennon
──「リョータッ私、今楽しいわ! なんでだろう? 車を走らせるなんて今まで何回もやってきたことなのに。だけど違うの!わからない、わからないけど楽しいよ! 」
「よっしゃ! この道からなら、そうだ! 海まで行くぞ! 零奈、俺の言うルートへ走らせるんだ!」
「OKリョータ! 私の腕で、2人だけで海まで行こう!」──
俺達の車は走る──ほんの一握りの自由を乗せて……
それでもこの時は、最高だった──
「真夜中を突っ走れ」 完