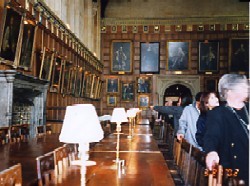3月27日・・・ストラットフォード・アポン・エイボン
前夜遅くにストラットフォード・アポン・エイボンのホテルに入りました。400年前の民家を改造したという、古めかしくも磨き込まれた木のおうちです。8畳ほどのホテルのロビーにあるTVは1970年代を思い出すような旧式、公衆電話も外の通りにしかないという堅実な雰囲気。でもそれだけにロマンもいっぱい香っていました。素敵なホテル・・・のはずだったのに、この後はホントに泣いてしまいました!
気持ち良くシャワーを浴びているうちにしだいにぬるくなり、そのうち水に!この日は肌寒くてストーブさえ欲しいくらいなのに・・・。エッー!
がたがたふるえ始めた未来には乾布摩擦をしてベッドに放り込みました。そうか、ここは400年前の家なんだ!ツアー客がいっせいにお湯を出してしまうとこうなるのも無理ない話・・・。甘かった!
しかし、翌朝の目覚めは爽快!窓辺に来てさえずる小鳥に起こされて映画みたいでした。おまけにホテルの庭向こうは見渡す限りの草原。朝露の中を靴をぬらしながら走り回ってサイコーでした。もしかすると夜中にゴーストさえ出たかもしれませんけど。あの冷水シャワーもよい思い出かも(?)
3日目は、いよいよシェイクスピアの故郷です。
 |
 |
 |
町の教会と観光バス
ストラットフォード・アポン・エイボンの街中を
走るツアーバス。主な見所を1時間くらいで回るので、利用すると便利。
|
エイボン川の風景
ゆるやかな流れのエイボン川。水鳥が静かに泳ぐ中を船で散策もできる。まるで時間が止まっているほどおだやかな春景色。
|
シェイクスピアの生家
木骨で組まれた建物は1564年生まれのシェイクスピアが大人になるまで住んだ家。大切に保存され外観は当時のままで各部屋も見学できる。しかしミシミシと床が鳴り、歩くのが申し訳ないほど。彼の父親は皮手袋職人で店屋だった。
|

|
 |

|
生家についての説明をするガイドさん
この町の専属のガイドさんは新聞関係の仕事をなさっていたという老紳士。英国では国家資格に準ずるガイド資格がないと観光客にも説明はできないそうだ。胸にバッジをつけておられた。
|
アン・ハサウェイの生家
町から2キロの所にあるシェイクスピアの妻の家。カーブを描くかやぶき屋根が美しい。妻のアンは彼より8歳年上で、こちらは豪農。部屋が12もあるこの家も当時の姿のままの形で保存がされている。ふたりが愛を語ったというベンチが室内に。
|
町のホテル
シェイクスピアの時代からなごりある家を改造した建物。今はホテルとなっている。1階の窓枠の上の花壇がかわいい。
|
当時の人々は欧米人といえど身長が低かったらしく、昔のベッドはどれも子供用かと思うくらいの1.6Mほどのもの。シングルベッドに
子供なら6人が(3人ずつ向かい合わせて)寝ていたとか。生家のサイン帳には有名人たちの訪問を示す直筆がズラリとか。みくも急いで書いていた。
シェイクスピアといえども、少年時代は、父親の仕事の手伝いに追われて勉強もままならなかったそう。そんな素顔に触れ、文豪がちょっと身近に思えてきた。
このあと、南東に約50キロくだりオックスフォードへ。

|
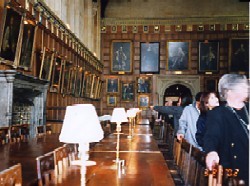 |

|
オックスフォード大・クライストチャーチ
1546年創立。45あるオックスフォード大学の中で最高の格式を持つ。19世紀には『不思議な国のアリス』の作者のルイス・キャロルがこちらの数学教授として活躍したことで有名。
|
クライストチャーチの大ホール
有名教授や首相など歴代卒業生、また大学ゆかりの人物の肖像画が壁全面を飾っている。正面はエリザベス女王様でした。写真一番前の女性はオックスフォードの観光ガイドさん。肖像画に囲まれて学生たちはどんな食事風景なのだろうか?
|
セント・メアリー教会
13世紀の後半に建てられた教会で、高さ62m。中央部分の丸い時計の上から学生たちが手を振っていた。ここから見る町が大変美しいらしい。塔の彫刻は遠くからでもくっきり見えて素晴らしい。
|

|

|

|
ボドレイアン図書館
クライストチャーチの中で一番大きな図書館。1602年の建造で640万冊の本を抱える。あのハリー・ポッターの映画のシーンで、ハリーたちが本を探すロケの場所になったことで注目も!
|
ラドクリフ・カメラ
17世紀にジョン・ラドクリフの遺産によって建てられた図書館。ドーム型の屋根が美しい。左のボドレイアン図書館と同じでツアーコースを申し込めば入場可能。
|
シェルドニアン・シアター内部
古代ローマの野外劇場をまねて1633年から30年かけて建築された円形のホール。今でも大学の重要な式典が行われる所。すり鉢上の木のいすの中にひときわ立派なのは、学長さんのいすだろうか(?)
|
町のとおりにある雑貨屋さんには大学のロゴの入った学用品やTシャツなどさまざまな日用品が並んでおり、町全体が荘厳さを兼ね備えた観光地という雰囲気でした。とは言っても、ここは若者の町!学生に人気のパブもいくつもあってかっこいい!
学内の売店には『アリス』関係の小物も多く、観光ガイドさんもさかんにルイス・キャロルについて話をされました。英国での時代を超えた『アリス人気』をひしひし感じました。
皇太子殿下や雅子妃殿下もこの地に数年学ばれたとのこと。どんな学園生活をお過ごしだったのでしょう。