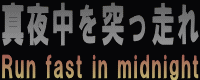
起きてみると、時計は九時をまわっていた。
卵の焼ける音が聞こえてきた。
そして、程よく焦げた良い匂い。俺はまだ眠気の残る身体をムッと起こして、台所へ行った。まあ当たり前といえばそうだろう。零奈が食事を作っていた。これがまた別の人間だったら、俺はこの世の中に嫌気がさして、フライパンで頭を叩いて自殺を図っている。
「起きたか。今食事を作っている。勝手に食材を使ってすまんな」
相変わらず女を感じさせない口調で淡々としゃべるなこいつは。これも暗殺者特有のものなのか。それはいいとして、こいつ一体何人分作ってるんだ?
目玉焼きはざっと5個、、、小さなフライパンに白身が溢れそうである。そして、味噌汁も5〜6人分はある。作りおきだろうと信じたかったが事実は違った。
零奈は目玉焼きを4個(つまり俺は1個)ぺろりと平らげ、小鍋についだ味噌汁をありえない速度で腹に収めた。さて、一体この細い身体のどこにそんな大きな胃袋があるのか? もしかしたら、こいつの内臓は胃しかないのかもしれない。興味津々で見ていると、今度はごはんをこれまたありえない速度で食べてしまった。
「こんなに食べたのは実際、久しぶりだ」
急にこんな事を言い出した。よく見ると顔が満足気である。
「これは、、、味噌汁というのだったよな? 」指で鍋をつついて教えろとせがむ。
なんだ、知らないで作ったのか?変な奴だ。
「私が3歳の時、5月8日の夕方5時34分頃だった。母が私に教えてくれたのを覚えていたんだ。残念ながら、味はそこまで再現できていない。たしかにぼしとか言う魚が必要だったのだが、ここにはない様なのでな」
こいつの言うことは突拍子がない。どこまで信じればいいのだろうか。大体、味噌汁の作り方を教えてもらった日や、時間を覚えている奴なんているか?昨日の暗証番号の長さといい、こいつの記憶力はちょっと異常である。
「それで、その母親は今どうしているんだ? 」あろうことか、気になった俺はつい聞いちまったんだ。零奈は普通の人なら、喋りたくないようなことを淡々と喋りだした。 聞いた俺が話すのをやめろと言いたくなるような話である。
零奈が言うには3歳の時の9月25日。それまで一緒に部屋でくつろいでいた母親が、急にベランダの方へ向かいだした。零奈は洗濯物を取り込むのだろうと思っていたが、その日は小雨の降る肌寒い日。
幼い零奈は、直感でこれは危険だと感じたらしい。
必死で止める零奈を振りほどき母親は、もたれかかる様にしてベランダから落ちた。
「それだけのことだ」
それだけ……? 聞いた俺が後悔するような話でも、零奈は別段普通に話した。
笑顔はないが、悲しみもない。ただただ、無表情である。
「で……昨日から今日までの話、どこからどこまでが本当なんだ?」
とたんに零奈の目がこちらを睨んだ。初めて見る怒りの表情だ。
「君は失礼な奴だな。今まで全ての話に嘘などない。そんなに疑うのなら、これで試してやってもいいんだぞ?」
零奈は、昨日見せた銃をこちらに向けた。やばいこいつ本気で怒ってる。マジで殺られる5秒前だぞ、俺。
「いやあごめんごめん。ただあまりにも俺には非日常的過ぎてよぉ」
「私にとってはあなた達の生活が非日常なのだ。その非日常に私がどれだけ憧れたことか……」
ぶつぶつ言いながら零奈は銃をしまった。
──危うく朝の食事が血みどろケチャップになるところだった。こいつ思ったより短気だ……話をあまり信じなかった俺も悪かったけどな。しかし、あんなに簡単に銃を出されちゃこっちだって困る。漫画じゃないんだぞ!
こいつとは色々話し合いが必要だ。よし手始めに。
「おい、まずその銃を何とかしてくれよ」
零奈はきょとんとした表情でこっちを見つめた。なにが……? ッて感じの顔である。
「一々ちょっとした事で命の危機にさらされちゃ迷惑だからよ」
「ちょっとした事……私の母が死んだこと……?」
「違うちがう! そうじゃない! だから、会話の弾みで怒ったんなら、こっちにだって謝ることは出来る。でもそれより先におまえが撃っちゃえば、それで終わりじゃないか。殴るとかならまだしも、銃は勘弁してくれってことだ!」
「……わかった。銃は出さない」そう言って、零奈はぼそりとこう呟いた。
「前私が殴った人は、当たり所が悪かったのかな?軽く殴って即死だったけど……」
俺は思わずため息が出た。やれやれ、殴るのも勘弁してもらわないといけないようだ。